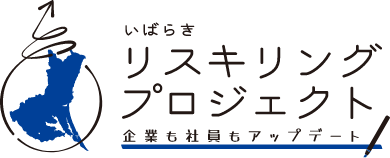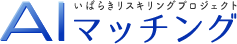福祉の中にIOTとDXを組み入れ
働きやすさ改革で離職率も低下
社会福祉法人 仁心会 (茨城県水戸市)
グループ企業に医療法人を持つ仁心会は「生活の質」と「日々の生活の中でできること」の維持と向上に努める特別養護老人ホームを運営。
福祉の現場で実践されるデジタルツールの活用と生産性向上をご紹介します。
県主催ワークショップで
リスキリングの真価に着目
「最初、リスキリングという言葉は「学びなおし」というような雰囲気で知ってはいたんですが、茨城県が主催するワークショップに参加させて頂いたことで、最初に持っていたイメージとは随分違ったことを覚えています」と話しはじめてくれた柳沼さん。仁心会の中で若くしてIOTの担い手となったリーダー的存在です。
そんな柳沼さんは県の研修を受け、リスキリングがただ学び直すだけではなく、その学びにが社内のDX化によって自分たちを再評価し、見える化することで生産性の向上などを招き、好循環を生み出すものだと知ったといいます。この学びが経営をしっかりとしたものにし、その先に新しい事業への転換もあるのだと認識。最初は自分たちがやっている以外の資格を取るようなものだと思ってはじめたことが、法人として企業として、事業転換をするだけでなく、いまの経営を強化していくものにも使えたことは驚きだったとか。「もちろん、個々の強化ではあるのですが、その個々の強化が会社の強化にしっかりつながることを実感できたのも学びでした」と振り返る柳沼さん。当初持っていた『リスキリング』という言葉のイメージと、その実態は大きく違ったと言います。
そんな柳沼さんたちが最初に取り組んだのはデジタルリテラシーの研修からはじまり、デジタルツールの研修へとステップアップ。簡易にプログラミングを使えるツールやAIを活用した手法などを学ぶ中で、見つけたのが『なぜなぜ分析』でした。問題とその対策に対して、その要因を探り、その要因を引き起こした原因まで突き詰めるトヨタ生産方式を構成する代表的な手法です。その『なぜなぜ分析』を行う中でデジタルツールを活用することが非常に有効であることを発見した柳沼さん。デジタルツールを使うことだけに着目するリスキリング研修が多い中、茨城県の研修会の中でデジタルツールを使うことはあくまでも手段であり、目的をしっかり持つことの重要性にも気づかされたといいます。

デジタルツールを活用し
業務改善をスムーズに実現
そんな柳沼さんは研修を受けた直後にサイボウズのキントーンを同社で導入。「研修前からテレビCMなどでその存在は知ってはいたものの、研修の中でその幅広い汎用性を知って導入を決めました。あとはチャットワークを導入し、グーグルカレンダーも組み込んで現在は運用しています。この導入によって、職員さんとの面談や新規採用のための面接などのスケジュール管理が一元化できたことで、僕自身の業務もスムーズに進むようになりましたし、離れた事業所間でのスタッフ同士の予定の把握もできるようになりました」と最初の一歩を振り返る柳沼さん。全ての職員にスケジュールの入力は難しいということから、グループごとにアプリへのスケジュール登録をお願いするなど、その運用にも工夫を重ねたといいます。以前はLINEビジネスを活用していたと言いますが、会社から職員への一方通行になりがちだったコミュニケーションが、互いのスケジュールが把握しやすくなったとこで相互通行になったこともIOT化したことで得られた大きな収穫だったとも。
さらに柳沼さんはキントーンの外部入力機能を使って、いままでは紙で行っていた年末の勤務評価を自動化。職員がパソコンやタブレット端末等で入力できるように工夫したことで、職員の手間も大きく削減されたと言います。
この結果を受けたこともあり、2024年に開業したもうひとつの特別養護老人ホームでは最初からデジタルツールを積極的に導入。以前は紙で捺印を繰り返していたものを、WEB上で承認を行うことで遠隔での業務も想像以上に業務改善が計れました。「もちろん、いろいろなデジタルツールを導入するに当って連携はとても重要です。弊社で言えば『会計』『介護請求』『勤怠』この3つが一気通貫で連携することは欠かせません。さらにこの3つのソフトと連携できるシステムを構築することが重要でした」と柳沼さん。プログラム導入初期のポイントを話してくれました。

リスキリングでスタッフのみならず
顧客満足度もアップ!
デジタルツールの導入とともに如実に結果が出てきたのは勤務時間の効率化だったといいます。この結果、同社の施設でも求められるケアマネジャーや介護福祉士の資格取得支援も円滑にできるようになったと言います。さらに茨城県の社会福祉協議会の研修などにも積極的に参加してもらえるようになったことに加え、以前は研修受講者を指名していたのが面談の中で希望を聞く時間も生まれるようになったとのこと。ユニットごとにタブレット1台・パソコン1台、PT・OT・管理栄養士・看護職員には1台ずつ配布し、各さらなる効率化を図っているといいます。そしてEラーニングを導入することで、新人研修やスキル研修を行う時間も積極的に増やせたといいます。
さらに、同社ではさらにエンジニアやデータサイエンティストを育成しようといています。この冬にはスタッフのひとりが新しく物品購入や在庫管理のシステムを組んでくれました。
そんな機運をさらに高めるために、県で提供しているリスキリングAIマッチングサイトを職場面談で活用しはじめました。現在事務局職員が、適性診断やスキル習得講座のマッチングの結果を参考にリスキリングに取り組んでいます。
この結果、仁心会では資格取得者が増え職員の所得向上にもつながり、離職率も大きく下がったといいます。「これが決め手でしたとはハッキリ言えませんが、以前と比べて明らかに離職率が減りました。これは面談がしっかりできていることなど、複合的な要因があると思っています。また、社内の改善もそうなんですがいままでエクセルで管理していた入所申込者の判定基準を見るための点数計算をしなくてはいけなかったのを、ソフト化することですぐに計算でき、一度計算しておけば簡単な個人情報を入れるだけで、施設間で共有できるようになったことが大きかったですね」と柳沼さん。
デジタルツールをグラデーション式で全職員に普及させることで大きな業務改善につながったと言います。その中で、経営基盤をしっかりさせながら職員のAI活用を望む柳沼さん。これから先にあるリスキリングへも積極的に取り組んでいきたいと語ってくれました。

社会福祉法人 仁心会
| 住所 | 茨城県水戸市酒門町1177-3 |
|---|---|
| 事業内容 | 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護ステーションの運営 |
| HP | https://swc-jinshinkai.com/ |