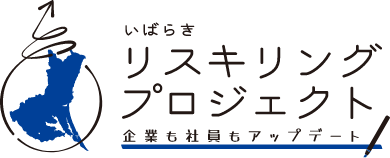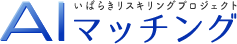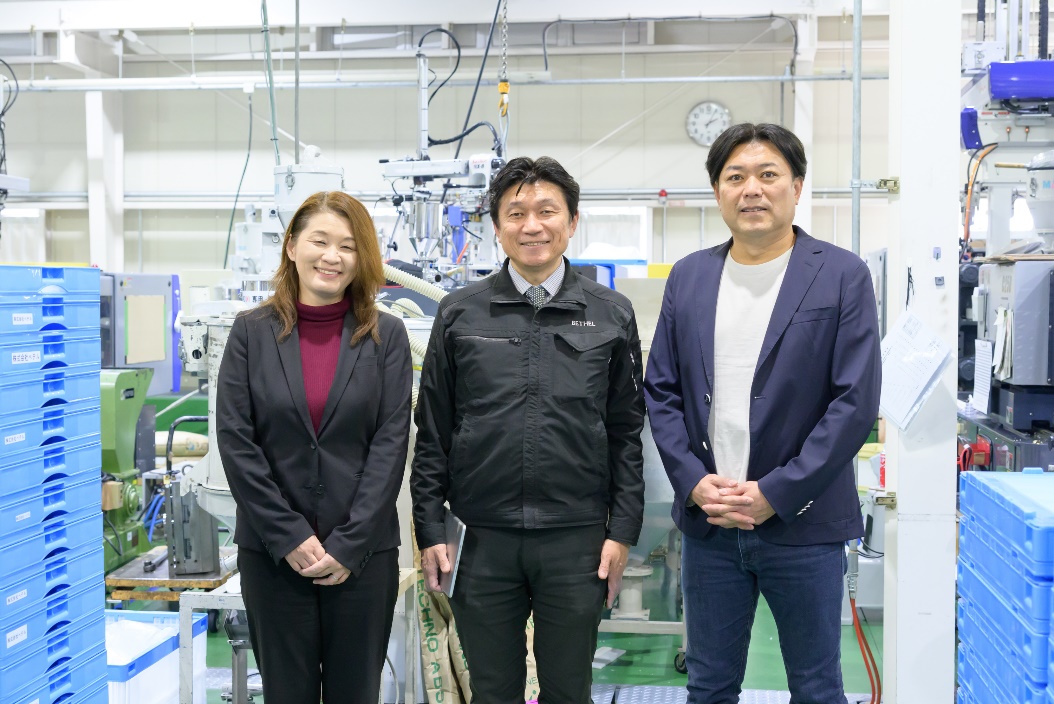
リーダーの抜擢と健全な危機意識の共有が
人を育てる
株式会社ベテル (茨城県石岡市)
主にメディカルコンポーネンツの分野でグローバル展開を活性化している株式会社ベテル。国外への販路拡大により、新たな顧客の獲得による事業拡大と増益を図っています。
人材不足が深刻化する中、社員のデジタル技術習得による生産性向上を図るため、リスキリングで習得したデジタルツールの活用による部署間での連携強化とデータドリブンな意思決定を実現し、令和6年度茨城県リスキリング推進企業等表彰でグッドプラクティス企業として注目を集めました。
そんなターゲットを絞った経営戦略を持ってリスキリングを実践する鈴木潤一代表取締役社長、その推進体制の先導者であるBMC事業部商品企画部企画課次長の北野早織さん、日本のリスキリング第一人者でいばらきリスキリング戦略アドバイザーの後藤宗明氏の三者が対談を行いました。
電子部品の製造で培った成形や組立技術を
医療・歯科機器に応用開発して海外展開へ
1973年に営業を開始して以来、電子部品の組立を中心に、超精密金型の設計・製作、プラスチック成形、熱物性測定、コンピュータソフト及びハードウェアの開発、精密アセンブリーとモノづくりの全ての領域において事業を展開してきた株式会社ベテル。海外進出の起爆剤となったのは、医療・歯科機器という他分野への応用開発です。
「リスキリングはデジタルのスキルに注目されがちですが、実は成長分野に移行していくところにスキルの価値があります。ベテルさんはグローバル輸出の業績が右肩上がりで伸びて成功されていますが、それと人材育成をどのように組み合わせたのか、深くお伺いしたいです」と後藤さん。
世界を目指すR&D(研究開発型)企業の新製品開発から輸出への意思決定、海外拠点の設置まで、これまで歩んだストーリーを辿るところから対談はスタートしました。
約40年間、大手企業の完全下請け業務が売上の5割を占めていたベテル。
鈴木さんは「経営は安定しているものの、利益率が比較的に低く、これまで培ったノウハウや技術を示しにくい状況でした。そのため、企業発展のために付加価値の高い事業展開をしていこうと、当時の社長(現会長)と方針を打ち立てたことが根底にあります」と他分野への新規参入のきっかけを語ります。
新しい分野に向けた機運が高まる中、2000年に念願のビッグチャンスが到来します。それは、同社が誇る超精密金型や精密プラスチック成形などの技術を応用した歯科治療部品の開発依頼です。
これまで扱ったことのないジャンルのOEMでしたが、試行錯誤の末に製造を始めると、売上高が徐々に成長曲線を描いていきました。
「2009年にリーマンショックで基幹事業の売上が約4割も下がったのですが、歯科医療だけは変わらず右肩上がり。やはり医療は景気に左右されず、危機に強い分野。これをもっと展開していこうと考えました」と鈴木さん。
こうして誕生したのが、歯科根管洗浄やバイオ実験などに使用される自社ブランドの「ベテルチップ」です。
海外への留学経験があり、英語が堪能な鈴木さんと常務を中心に、2010年から欧米の医療関連の展示会に出展すると、ドイツでの商談を足掛かりに海外展開が本格化。アジアやイスラム諸国へと商圏を広げ、ベトナムに新たな製造拠点を設立するなど、生産力強化を図っていきました。

グローバルに顧客拡大を図るため
語学のリスキリング体制を推進
ベテルの海外事業は、本社の歯科・医療機器、ハドソン研究所で製造する熱物性作成装置、ベトナム工場の3つの窓口があり、海外事業や輸出に関わる従業員は主に6人。新規で採用した人材ではなく、海外展開前から在籍している従業員が担当しています。
海外展示会への出展経験があり、その難しさを知る後藤さんは、「展示会のブースで商談ができるレベルの語学力を持つ従業員の方はいたのですか?」と尋ねると、「北野をはじめ、当時はまだ英語が話せなかった従業員達も連れていきました。いくら社長が先導しても、次に続く人がいるかというのは難しい課題ですから」と鈴木さん。
グローバルに顧客拡大を図るため、必要不可欠な英語のスキルを習得しようと、まず語学のリスキリング推進体制を構築しました。
営業部門に英会話が可能な担当者を配置し、受講者対象にタブレットやノートPCを貸与し、学習しやすい環境を提供。就業時間内に定期的な勉強会を実施し、通信研修も活用して、社内にリスキリング文化を浸透させていきました。
鈴木さんは「『いばらき中小企業グローバル推進機構』の通訳派遣のサポートを活用しながら、語学を勉強している従業員に任せています」とリスキリングの成果を語ります。
また、グローバル展開に伴い、顧客や市場の急速な変化への対応を迫られたベテル。
データやデジタル技術を活用し、社内を変革しながら顧客に新しい価値を提供することで、競争優位性を確立しようと、北野さんが旗振り役となり、DX推進係を新設する組織改革を提案しました。
すぐさま、上層部のGOサインが出ると、DX推進委員会を立ち上げ、茨城県産業技術イノベーションセンターを通じてDX関連のリスキリングプログラムを組み、部署横断的な体制を構築し、連携を強化していきました。
「波に乗るタイプで流行り物が好きなだけかもしれないです」と笑い混じりで語る北野さん。
「でも、中小企業は一歩前に出ないと。他社と同じことをやっていたら絶対に勝てない。当社は中小企業では珍しく、社長や上司が勉強をやりなさいと促しますし、基本的に自分でやりたいことに対してノーと言われない。失敗しても褒められる風土が根付いているんですよ」と提案した理由を明かします。
「従業員の方から『やりたい』と伝えられる土壌は、大切なポイント。ほとんどの企業ではそれが機能していないですよ」と後藤さん。
海外の展示会で代表者の一人として矢面に立つ場面が多い北野さんは、「私の部署である商品企画部、展示会も一緒に取り組む技術開発部は、お客様のところに訪問してオーダーを聞き、クレームの1発目を受け続けている。技術なり何かを上げていかないと維持できないとシビアに感じているメンバーが多いのです」と正しい危機感からの行動だと語ります。

スキルで評価した人材を抜擢
公平性の高い人事の仕組みづくり
後藤さんは、リスキリングとは“諸刃の剣”と表現します。
「リスキリングは2つの壁があります。1つは実際に学んだことを仕事で活かせる受け皿があるか。もう1つは取り組んだことに対して評価してもらえるかどうか。これがないと転職を考えてしまうのですよね。リスキリングに成功している企業の共通点は、トップが資格手当や給与を上げるなど、処遇に繋げることを明確に伝えていることが挙げられます」と語ります。
ベテルではDX推進委員会やDX推進チームへの参画者30~40人に対しては、賞与で手当加算を実施するとともに、業務改善や生産性向上への功労者には社長賞を授与しています。
また、DX推進委員会の活動内で立ち上げた新規プロジェクトの中心メンバーに抜擢するなど、評価や処遇の改善を試みています。
現在は次長を務めている北野さんですが、常務の新規営業の補佐役として採用された人材。当初は幹部候補ではありませんでしたが、グローバル展開での実績、DX推進委員会やリスキリング導入の取り組みが評価され、管理職に抜擢された一人です。
後藤さんは「海外でリスキリングが施策として当たり前になっている理由は、まさにそこです。かつて日本では総合職や一般職というルートが決まったカテゴリーがあったり、欧米では人種や家柄などで昇進への制限があった中、スキルでフェアに評価することで、やる気がある人が眠らずに伸びていく。公平性の高い人事の仕組みづくりの一環として、リスキリングが注目されているのですよ」と称賛しました。
ベテルではその他にも、社員に年1件以上の外部研修の受講を推奨し、ジェトロの貿易実務講座など会社が許可した研修に関しては、就業時間内での受講を認めるとともに、スキル習得に係る費用を全額負担。
会社の発展に関連する意欲的な研究などに対しては、社会人大学生としてオンライン講義の受講や研究室への通学を業務として認めて後押ししています。
鈴木さんは「新しいことをやって輝き出した人を周囲が見て、『私もやりたい』といいスパイラルが生まれる仕組みづくりをプロデュースしていきたいですね」と今後の展望を語ります。

リスキリングでDX人材を育成
後継者が次々と育つ、活力のある組織に
企業の寿命は30年と言われている中、創業50年余りのベテルは組織としての「死」を乗り越え、次の30年も元気ある企業となるために、「ベテル・ボーン・アゲイン・プログラム(B-BAP)」を策定しました。
鈴木さんは、リスキリングによるDX人材の育成、ビジネスモデル改革、業務改革に取り組み、活力のある組織に再編成したいと語ります。
「行き着きたい場所、つまりベテルの夢は、イノベーションを起こして世界にアピールすること。製造の中でプラットフォームを構築し、新しい付加価値を作りたいと考えています。新たなプラットフォームをつくるのは、大きな会社ですし、新システムの導入やサプライチェーンを巻き込んでできると思いますが、我々はそういう立場ではない。今後は技術的な部分は不可欠になるので、リスキリングに取り組むDX人材の中から、旗振り役の私がいなくとも、勝手に進んでいくようになればいいと思っています」
ベテルでは部署ごとの後継者育成や、リスキリングによって技術者に対人交渉スキルを習得させ、海外でのOEM生産に舵を切るサクセッションプランニングを構想中。
今後もDX推進を強化し、新規事業プラットフォームをつくるため、茨城県産業技術イノベーションセンターのセミナーや研修、茨城県データサイエンティスト育成講座などを活用していく方針です。
最後に後藤さんは「リーダーの抜擢と健全な危機意識の共有が人を育てる」というベテルのキャッチフレーズを考案しました。
「人が育ち、ビジネスが大きくなった歴史は、社長によるリーダーの抜擢と、健全な危機意識をちゃんと共有できていたので、それを見て、従業員の方達が自ら手を挙げて学ぶようになった形ですよね」
鈴木さんは「今までリスキリングになびかなかった人が、自ら取り組むようになるのが今後の展開です」とさらなる躍進への意欲を示しています。

いばらきリスキリング戦略アドバイザー後藤宗明氏 プロフィール
富士銀行(現みずほ銀行)入行。渡米後、グローバル研修領域で起業。帰国後、米国の社会起業家支援NPOアショカの日本法人を設立。米フィンテックの日本法人代表、通信ベンチャー経営を経て、アクセンチュアにて人事領域のDXと採用戦略を担当。その後、AIスタートアップのABEJAにて米国拠点設立、事業開発、AI研修の企画運営を担当。10年かけて自らを「リスキリング」した経験を基に、リクルートワークス研究所特任リサーチャーとして「リスキリング~デジタル時代の人材戦略~」「リスキリングする組織」を共同執筆。2021年、リスキリングに特化した非営利団体、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。
株式会社ベテル
| 住所 | 茨城県石岡市荒金3-11 |
|---|---|
| 事業内容 | 医療機器の開発、製造、販売・電気部品及び機械部品の組立、製造・プラスチック精密金型設計、製造、販売、金属部品加工・熱物性測定に関する装置の開発、製造、販売・ギヤードモータ事業 |
| HP | https://www.bethel.co.jp/ |